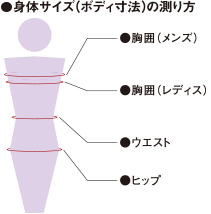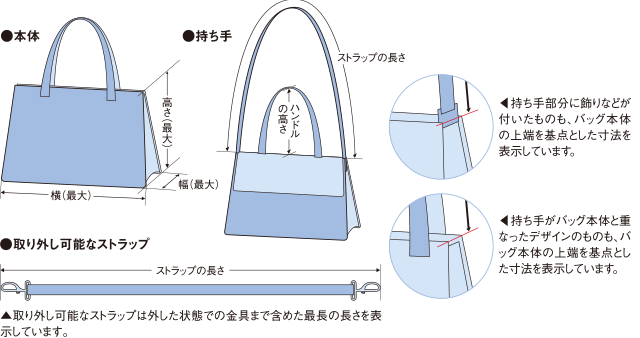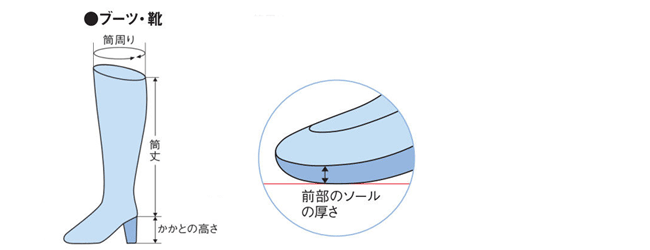- 格調高い伝統の雛人形をモダンに愉しむ。
- 平安時代、公家の女児の人形遊びが起源とされる雛祭り。江戸時代中期になると女児の健やかな成長を願う行事として庶民にも普及し、雛人形は京都とは異なる江戸独自の姿が確立されました。これが、現代に続く江戸衣裳着人形です。伝統工芸士、横山薫さんは、その伝統を受け継ぎ人形制作を続けており、確かな技術と情熱を持った人形作りに定評があります。
- 装束の隅々までこだわった美しい仕立てに気品が薫る。
- ご紹介するのは、横山氏が手がけた「正絹名物裂衣裳着/親王飾り」。木胴、木手を使い、女雛は伝統的な「本着せ付け」で衣裳を着せ付けました。人間が実際に着物を纏うように一枚の着物を着せていく本着せ付けは、少しの歪みが全体に影響を及ぼすため非常に難しく、できるのは人形師の中でもほんの一握りだといいます。横山さんはこの本着せ付けを体得する数少ない人形師の一人。本着せ付けをした女雛は、自然な衣裳のボリュームと、人間らしいしなやかな身体のラインが見事に表現されています。一方、男雛は上衣と下衣を分けて着せる一般的な並着せを採用。緻密な柄合わせが光ります。人形の中心を意識して左右のバランスを見ながら均等に着物を重ね、美しい仕上がりを実現しました。また、着せ付けの後に腕を曲げる「腕折り」も難しいとされる工程のひとつ。衣裳に余分なシワがなく、腕が左右対称に綺麗に揃っているところにも高い職人技が窺えます。平安時代の十二単の構造に忠実に基づき、装束の細部までこだわる、江戸衣裳着人形の伝統である「本仕立て」が活きたつくりも特徴。裾を見ていただければ、着物の重ねが繊細に再現されていることがわかり、本仕立てがもたらす優雅さと気品が際立ちます。男雛、女雛の衣裳はいずれも正絹の名物裂、正倉院丸唐花文様を贅沢に使用。大輪の唐花文様が格調高く華やかな印象を醸し、特に女雛は色合わせの妙も魅力です。お顔は人形界の巨匠、熊倉聖祥氏の原型を使用。屏風には格子や唐草文様を配し、和のしつらえを意識しつつ現代空間にも馴染むモダンな雰囲気が漂います。全体的にすっきりとスタイリッシュにまとめることで、高度な技で作り込まれた雛人形がいっそう趣深くなり存在感を放ちます。伝統とモダンが見事な調和を成した雛飾りは、季節が巡るたびに飾りたくなることでしょう。
| セット内容 | 男雛、女雛、雛人形持物(笏、扇)、親王台×2、菱台×2、三方、燭台×2、桜、橘、屏風、飾り台、敷布 |
|---|---|
| サイズ(約) | 飾り時=幅70cm×奥行41cm×高さ40cm、男雛=高さ23cm(纓含む)、女雛=高さ15cm |
| 重さ(約) | 4.8kg(総重量) |
| 材質 | 雛人形=石膏、木胴、衣裳=正絹、ポリエステル、他、屏風・飾り台=中質繊維板 |
| 付属品 | 木製立札付 |
| 制作 | (株)久月 |
| 原産国 | 日本 |
| その他 | ※手作りのため、柄の出方が写真と異なる場合があります。 ※商品の交換・返品はお受けできません。 |

昭和48年より雛人形制作を続ける横山薫氏。平成14年、東京都知事認定の伝統工芸士、平成15年に台東区伝統工芸士の資格を取得。伝統と格式を重んじる先代、横山富久氏の教えを守りつつ新しい表現を取り入れています。
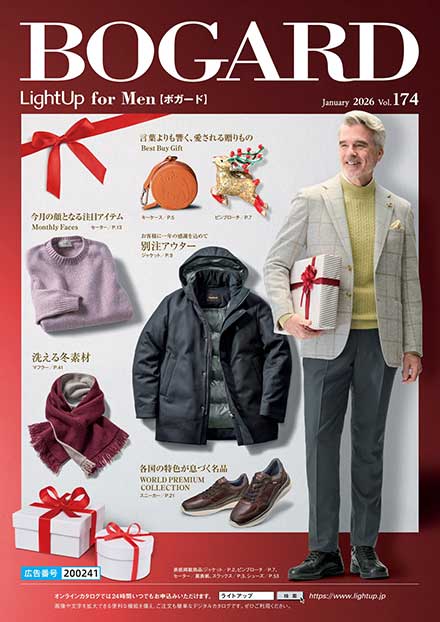
 Miss Kyouko/ミスキョウコ
Miss Kyouko/ミスキョウコ William Morris/ウィリアム・モリス
William Morris/ウィリアム・モリス 当社限定ビューティーアイテム
当社限定ビューティーアイテム 【特集】〈銀座 梅林〉国産ヒレ肉の特製カツ丼の具
【特集】〈銀座 梅林〉国産ヒレ肉の特製カツ丼の具