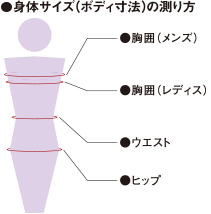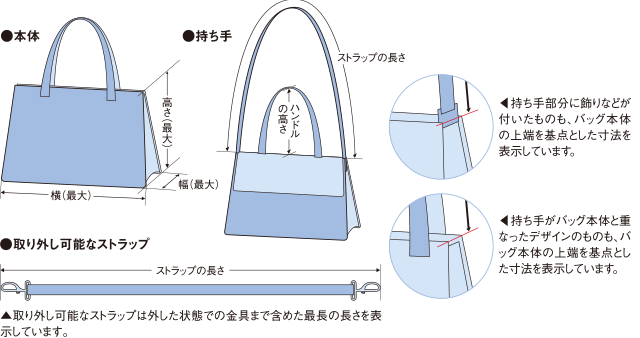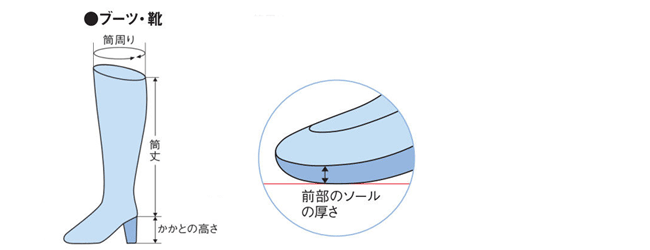- 桜の季節を堅牢優美な輪島塗のぐい呑で愛でる。
- 江戸時代前期に確立され、品質、耐久性ともに日本を代表する伝統工芸、輪島塗。こちらは、輪島市に工房を構える老舗〈中島忠平漆器店〉が手がけたぐい呑です。「月に照らされた夜桜、満開の桜、葉桜をモチーフに考案。色漆と沈金の色彩バランスにこだわりました。曲面に正確に柄を彫る沈金師の高度な技にもご注目ください」と先代の故 中島利雄氏が語っていたぐい呑。色漆は気温や湿度による漆の乾き具合や顔料の量によって発色と強度が異なるため、分量の調節が難しいといいます。輪島塗は分業のため、塗りを施した後は専門の沈金師がその上から転写した図案に沿ってノミで彫り、溝に金を埋め込む沈金で精緻な桜を表現しました。
| サイズ(約) | 最大径8.6cm×高さ4.6cm |
|---|---|
| 重さ(約) | 42g |
| 材質 | 天然木(欅)、漆塗り仕上げ |
| 原産国 | 日本 |
| その他 | ※漆を使用しているため、漆にかぶれやすい体質の方がまれにかぶれることがあります。 ※手作りのため、色調、柄の出方、サイズ、重さが写真・スペックと異なる場合があります。 |
中島忠平漆器店
明治5年、初代が現在の輪島市鳳至町に居を構え、漆師・忠平として創業した漆器の名店。

2023年に〈中島忠平漆器店〉の六代目店主となった中島悠氏。

沈金は沈金師が金箔を埋め込むために、転写した線に沿って沈金ノミで溝を彫ります。
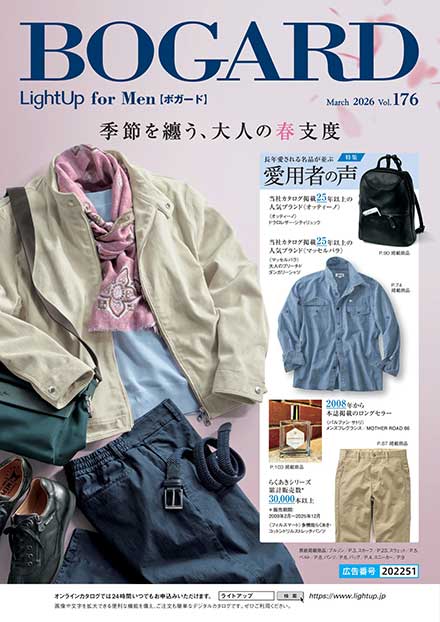
 Miss Kyouko/ミスキョウコ
Miss Kyouko/ミスキョウコ William Morris/ウィリアム・モリス
William Morris/ウィリアム・モリス Salon de GRANDGRIS
Salon de GRANDGRIS 【特集】三國清三のまかない飯 12ヵ月頒布会
【特集】三國清三のまかない飯 12ヵ月頒布会