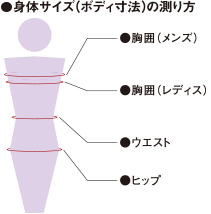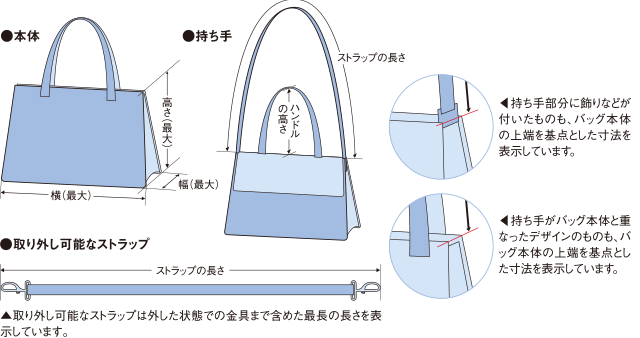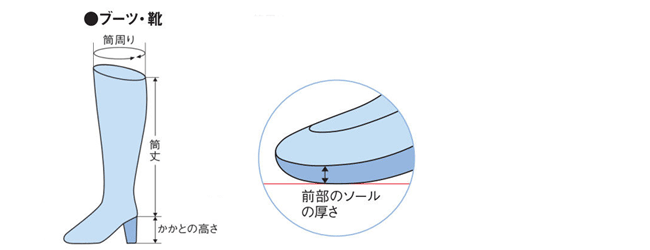- 万葉の時代を見事に再現。無邪気に遊ぶ童に心が和む。
- 大正8年に創業し、江戸時代から続く伝統の技と古典美を継承する江戸木目込人形の名門〈真多呂人形〉。こちらは、万葉集に出てくる万葉童を表現した「明日香童」です。原型を制作したのは二世 真多呂氏。先代が遺した作品を今も大切に受け継いでいます。男の子は手を広げて軽やかに足を上げ、はつらつと。女の子は控えめな動きながらも、その手や首の角度から愉しく遊んでいることが窺えます。顔を傾けるちょっとした角度や手の仕草などで童たちが醸し出す雰囲気が変わるため、二世 真多呂氏はこの愛らしさを損なわないよう、動作の一つ一つに苦心したといいます。動作に合わせて揺れる衣裳までも繊細に表現されており、二世 真多呂氏の観察眼や細部へのこだわりにも驚かされます。豪華な衣裳は、人形のために特別に織られた「龍村美術織物」の生地。「人形はあくまで皆が愉しめるもの、眺めているうちに心が和むものがいいと思うのです」と三世 真多呂氏が語るように、愛らしい童の姿は眺めるほどに童心の世界へと誘ってくれそうです。
| お届け予定 | お届けはお申込みより約1〜2ヵ月間を要します。 |
|---|---|
| サイズ(約) | 男の子=高さ15cm、女の子=高さ15cm、飾り時=幅45cm×奥行30cm×高さ21cm |
| 重さ(約) | 男の子=170ℊ、女の子=134ℊ、総重量=1.8kg |
| 材質 | 本体=桐塑、衣裳=正絹(西陣織)、台=中質繊維板にカシュー塗り |
| 仕様 | 立札付 |
| 原産国 | 日本 |
| その他 | ※手作りのため、色調、柄、サイズ、重さが写真・スペックと異なる場合があります。 ※商品の交換・返品はお受けできません。 |
真多呂人形
大正8年創業、江戸木目込人形の名門〈真多呂人形〉。木目込人形は、江戸元文年間に京都の上賀茂神社に使える宮大工が神事に用いる細工物の余り木でつくった賀茂人形が始まりです。鴨川のほとりの柳の木を素材に木彫りを施し、神官の衣裳の端布を木目込んだものでした。現在は桐塑が使われていますが、職人の繊細な技の粋を凝らしたもので、日本を代表する人形芸術のひとつとされています。上賀茂神社から木目込人形の高い技術と古典的な美を受け継いだのが、初代金林真多呂氏。天皇陛下への献上をはじめ、各国首脳への贈り物でも重用され、人形制作の第一人者として賞賛を集めた人物です。その後、二世 金林真多呂氏が上賀茂神社より賀茂人形の正式伝承者として認定。現在は三世が伝統の技術を受け継いでいます。
江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)
18世紀に京都で発祥。「木目込み」とは胴体の原型に溝を彫り、宮廷装束を再現した布地を貼り付ける日本独自の技法です。まるで衣裳を纏っているかのような自然な佇まいが魅力です。

 Miss Kyouko/ミスキョウコ
Miss Kyouko/ミスキョウコ William Morris/ウィリアム・モリス
William Morris/ウィリアム・モリス VECUA GRAND PREMIUM
VECUA GRAND PREMIUM 【特集】〈銀座 梅林〉国産ヒレ肉の特製カツ丼の具
【特集】〈銀座 梅林〉国産ヒレ肉の特製カツ丼の具