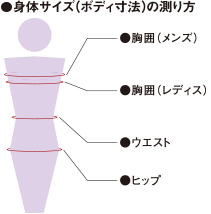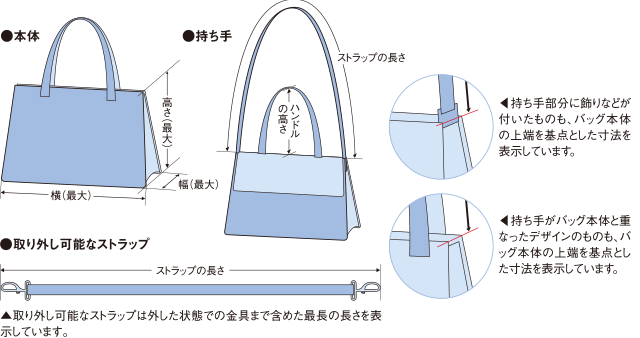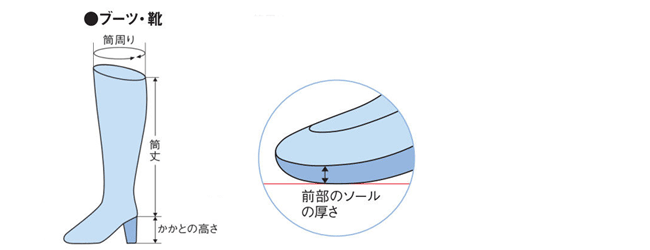- 柿渋の趣漂う、粋な江戸扇子。
- 趣ある色合いが印象的な「寺社好み江戸渋扇」。江戸扇子の伝統工芸士の松井宏氏が、僧侶が使う大ぶりで頑丈な扇子にヒントを得て製作したものです。紙と骨の製作以外、30以上もの工程すべてを一人で行う松井氏。こちらの扇子は骨数を15間と控えることで京扇子とは異なる力強い美しさを表現しました。扇面には柿渋で染めた刷毛目の残る和紙を、骨部分には煤竹風に唐木色に染めた竹を使用しており枯淡の味わいが宿る仕上がりです。
| サイズ(約) | 開いた時=最大幅39cm、折りたたみ時=幅2.2cm、長さ24cm |
|---|---|
| 重さ(約) | 30g |
| 素材 | 扇面=和紙、骨=竹 |
| 原産国 | 日本 |
| その他 | ※木目、色調、重さが写真・スペックと異なる場合があります。 ※天然染料を用いているため、使用開始時に柿渋特有の匂いがすることがあります。 |

江戸扇子職人である松井宏氏。「扇子は持つ人の品格を象徴するものです。江戸の粋が息づく扇子で涼を感じてください」
職人の技と伝統の結晶—粋な江戸扇子の製作工程

- 1.【平口開け】表裏をそれぞれ1.5枚分の厚さになるよう裂きます。
- 2.【折り】湿らせた扇面を型紙で挟み折り目を付けます。
- 3.【中差し】竹を通して、骨を入れる穴を開けます。
- 4.【吹き】中差しした穴に息を吹き込み膨らませます。
- 5.【中付け】扇面の大きさに合わせて切った骨を入れます。
- 6.【親付け】親骨と扇面を糊付けし、親骨の形を整えます。
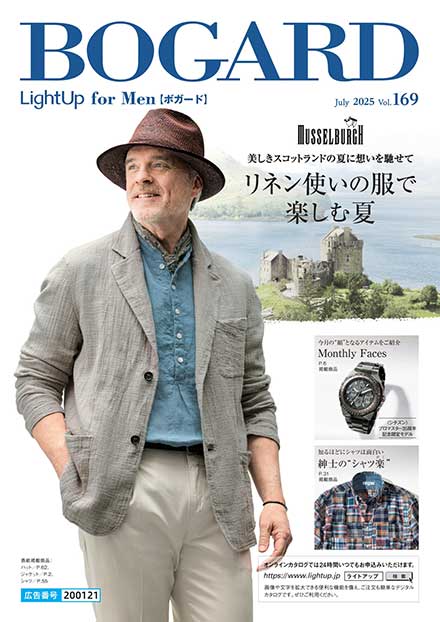
 Miss Kyouko/ミスキョウコ
Miss Kyouko/ミスキョウコ William Morris/ウィリアム・モリス
William Morris/ウィリアム・モリス VECUA GRAND PREMIUM
VECUA GRAND PREMIUM 【特集】〈銀座 梅林〉国産ヒレ肉の特製カツ丼の具
【特集】〈銀座 梅林〉国産ヒレ肉の特製カツ丼の具